相続で生命保険が重宝されるわけ

相続対策で注目される「生命保険」
相続が発生すると遺産分割や相続税の負担など、さまざまな課題が浮上します。
これらの課題に対処するための手段として「生命保険」が重宝されています。
この場合の生命保険とは、亡くなった人の死亡保険金の受取人を相続人などにしている保険を指します。

生命保険が重宝される理由
生命保険が相続対策として重宝される理由を6つのポイントで解説します。
相続税の非課税枠
死亡保険金には法定相続人が受け取る場合に適用される非課税枠があります。
非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で、この枠までは相続税がかからずに保険金を受け取ることができます。
例えば、法定相続人が3人の場合、「500万円×3人」で1,500万円までの死亡保険金が非課税となります。
相続発生時に預貯金などの相続財産であれば、そのまま相続税の課税対象となりますが、この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することにつながります。
現金の確保
相続税は現金で支払う必要があります。
しかし、相続財産が不動産や株式などの資産に偏っている場合、現金化するのに思いのほか時間がかかり納税資金を用意するのが難しくなることがあります。
生命保険金は現金で支給されるため、納税資金として利用することができます。
相続の発生後、必要書類を保険会社に提出すると1週間程度で受け取ることができるので、葬儀費用や当面の生活費、緊急の支払いなどにも使えるお金として役立ちます。
銀行口座の預金などのように資産凍結になってしまうこともありません。
渡したい人に確実に渡せる
生命保険金は受取人を指定することから、特定の相続人や親族に確実に資金を渡すことができます。
例えば、障害のある家族に渡して、生活支援に充てることや家業を継ぐ子に渡すことなど、財産を渡したい人に渡すことができます。
受取人の財産になる
生命保険金は受取人固有の財産として扱われるので、遺産分割協議の対象にもなりません。
またマイナスの財産の方が多い場合に相続放棄をするケースでも、生命保険金は固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。(ただしこの場合、相続税の非課税枠は適用されません)
生命保険金は民法では相続財産とはみなされないためです。
ただし、税法では相続財産とみなされるので相続税を算出する際には含まれます。
そのため、非課税枠の活用が重要となるのです。
資産運用商品としての活用
生命保険商品の中には運用利率が高いものや外貨建ての保険商品など、資産運用効果を兼ね備えた商品もあります。
ただし、運用リスクや為替リスクには十分な配慮が必要です。
契約を見逃さない制度の存在
生命保険には契約照会制度があり、相続人や受取人が生命保険会社に契約の照会をすると、生命保険会社が未請求の保険があった場合でも存在を知らせてくれます。
この制度により、保険金の存在を見落とすというリスクも減らせます。
生命保険活用の注意点
相続対策として生命保険を活用する際の注意点があります。
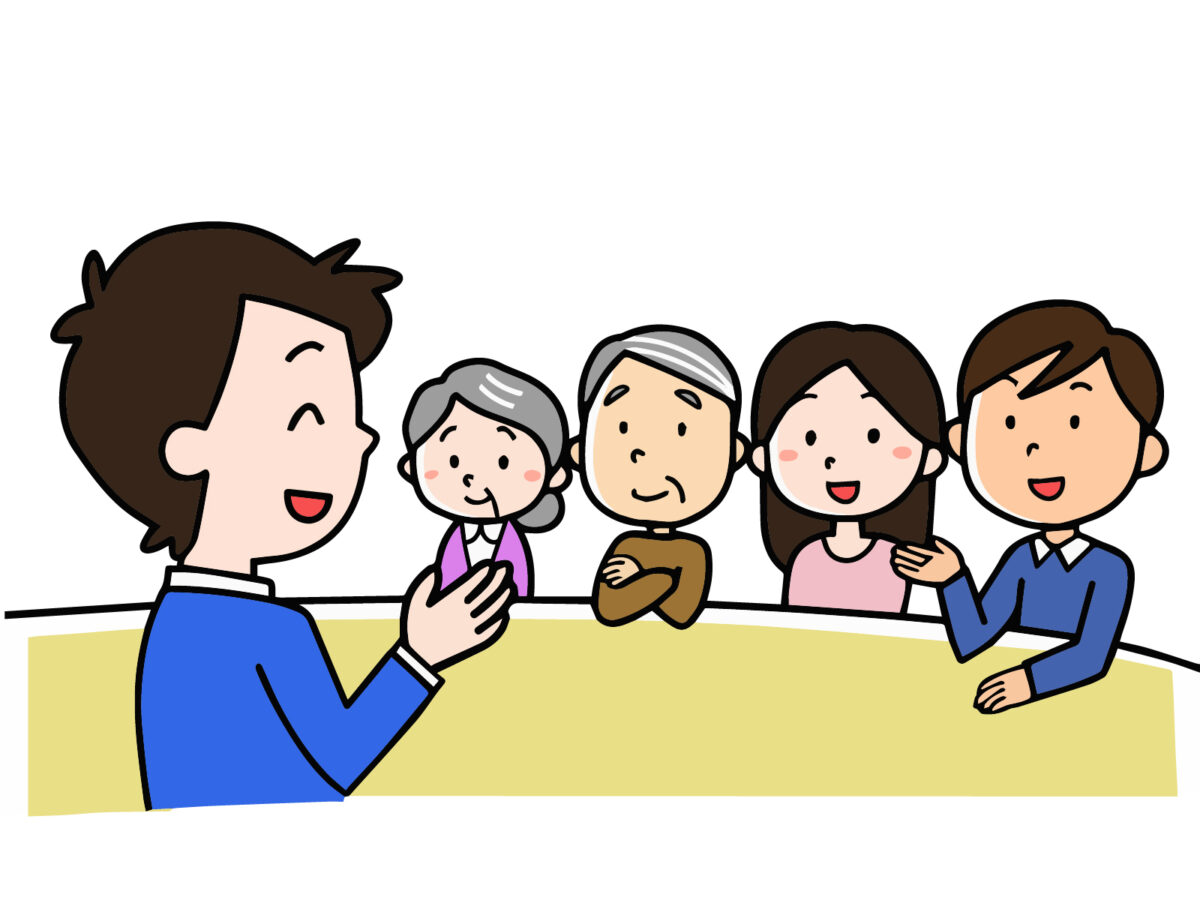
相続税の非課税枠を有効に活用するために、適切な保険金額を設定することが重要です。
もともと大きな控除枠を持つ配偶者を受取人にするよりも、子を相続人にすることで非課税枠をより有効に活用することができるケースもありそうです。
一方、特定の受取人に多額の保険金が渡るように設定すると、思わぬ相続トラブルにつながることがあります。
家族間で誰を受取人にしてどれだけの保険金を設定したかの認識を共有しておくことも大切です。
税理士やファイナンシャル・プランナーなどに相談し、ご家族の状況に合った生命保険の活用をすることで、相続をスムーズにすすめることができそうです。


