生前贈与は本当に相続対策になるのか

生前贈与は相続税の節税対策か
「生前贈与は相続税の節税対策として有効」という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
使い方によっては有効な手段になることもありますが、実は制度改正があって状況が変わってきました。
また適切に行わないと逆に税の負担が増えてしまうこともあるため注意が必要です。
生前贈与は、若い世代に早めにお金を引き継ぐことで「活きたお金の使い方」をするためにこそ有効なのかもしれません。

なぜ生前贈与が相続税の節税になるのか
相続税は、亡くなった人の財産を相続人が受け取る際に課税されます。生前贈与をすることで、相続時の財産を減少させることができ、結果として相続税の課税対象額を抑えられます。
これが相続税の節税対策として有効だとされる理由です。
贈与税の対策が大切となるわけ
ただし、一方で贈与に対しては贈与税が課税されるので、贈与税の対策をどのようにするかが大切です。
贈与税額が高くなってしまい、結果として相続税で支払うよりも多く支払ってしまったということがないように慎重に考えることが必要です。
贈与税は相続税の補完税とされていて、そもそも贈与財産は相続財産の範囲に属するものだとする考え方があります。
つまり「相続時に相続税で支払うか、贈与した際に贈与税で支払うか」ということになります。
お金を活かす使い方としての贈与
原則としてはそうなるのですが、経済合理性を考えると、資産移転を進めて若い世代が「活きたお金の使い方」をするほうが、高齢層が手元に置いたままにしておくよりもずっと合理的と言えます。
贈与にはさまざまな非課税制度が設けられていて、若い世代への資産移転を進めることを促しています。
生前贈与の非課税制度
①暦年課税制度
暦年課税とは、1年ごとに贈与税を課税する制度です。贈与税の一般的な制度です。
110万円の非課税枠があります。贈与を受け取った人(受贈者)が1年間に受け取った贈与の合計額が110万円(基礎控除額)以下であれば、贈与税はかかりません。
つまり、子や孫などに110万円を超えないように贈与することで、相続時の財産を減らすことができるわけです。
110万円を超える部分が贈与税の課税対象となります。
また相続が発生すると、相続前の贈与をさかのぼって、贈与した財産を相続財産に加算して相続税が課税されるルールがあります。
かつては相続開始前3年以内の贈与までさかのぼりましたが、2024年1月1日から制度が変更され7年以内の贈与が対象となりました。
(加算対象期間は2024年から漸次延長され2031年から7年間となる。延長された4~7年前の贈与については総額100万円までは加算の対象外)
さかのぼる期間が長くなるので、注意が必要です。
関連リンク:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
また連年贈与とみなされないようにすることも重要なポイントです。
②相続時精算課税制度
例外的な課税制度です。贈与時にいったん贈与税を納付しておき、贈与者が亡くなった時に贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算し、相続税額からいったん支払った贈与税額を控除します。贈与税額の方が多かった場合は、還付されます。
この制度でも1年ごとの110万円の基礎控除があります。さらに累計で2,500万円の特別控除があります。この控除額が贈与税の計算では非課税となります。
ただし特別控除の2,500万円は相続税を計算する際には加算されるので、節税効果はほぼありません。
贈与時よりも相続時の方が値上がりすることが確実な資産であれば、早めに贈与することで低い評価額で税金の計算がされるのため節税効果があるとされています。
しかし、値上がりすることが確実な資産をどう見つけるかはかなり難しいと言えます。
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して贈与する場合に選択することができます。一度、選択すると同じ贈与者からの贈与については、暦年課税に戻すことはできません。
③配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除額110万円のほかに、最高2,000万円を控除することができる制度です。
適用の条件が細かく定められているので注意が必要なことに加え、不動産の所有権移転では、登録免許税や不動産取得税などの費用が発生するので、税務上有利であるとは限りません。
④その他の非課税枠
住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金の贈与に対しても非課税枠があります。
適用条件が細かく定められていたり、使途が限定されていたりするので注意が必要です。
生前贈与で注意すること
贈与については、ルールが細かく定められています。
贈与には契約が必要です。税務署から「贈与ではなく名義預金」などと指摘されないように、贈与であることを証明する契約の書面等を作成することなどが大切です。
生前贈与は使い方によっては、ある程度の税金対策ができることもあります。税理士など専門家のアドバイスを受けながら進めるのが重要です。
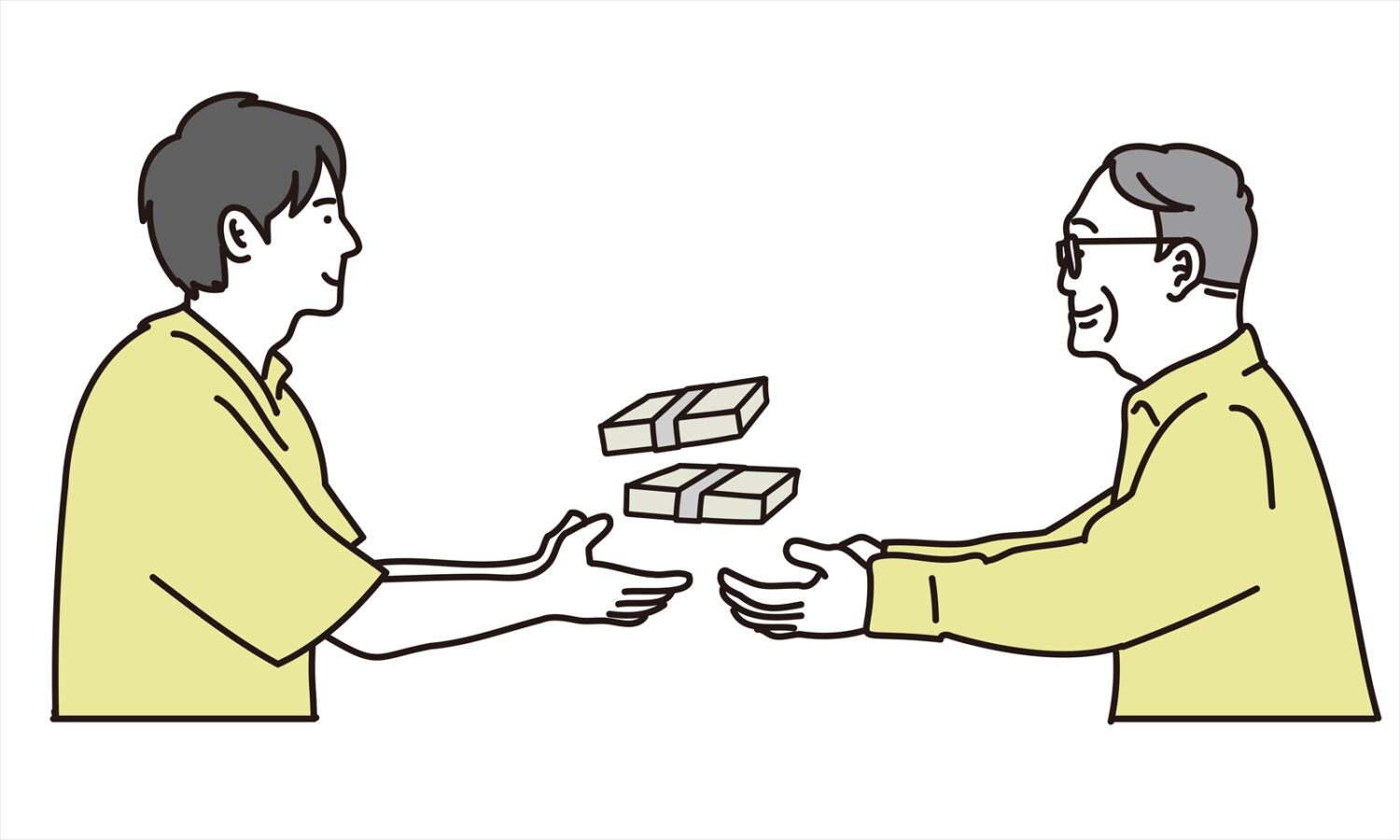
生前贈与の本当の役割
生前贈与は相続では財産を渡せない孫への資産移転をすることも可能となります。
若い世代への資産移転が「活きたお金の使い方」につながるという意義の方が、税金対策よりも大切なことなのかもしれません。
<用語>
贈与税の配偶者控除 住宅取得資金等の贈与の非課税枠 教育資金の贈与の非課税枠 結婚・子育て資金の贈与の非課税枠 直系尊属 直系卑属


