家族信託の費用は高いのか安いのか

認知症への備えとしての家族信託
認知症による資産凍結のリスクを避ける方法として注目されているのが「家族信託」です。
家族信託は財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産を託して、管理や処分を任せる仕組みです。財産の管理や相続をスムーズに進めるために活用されています。
今回は家族信託についてと、その費用が高いのか安いのかを解説します。
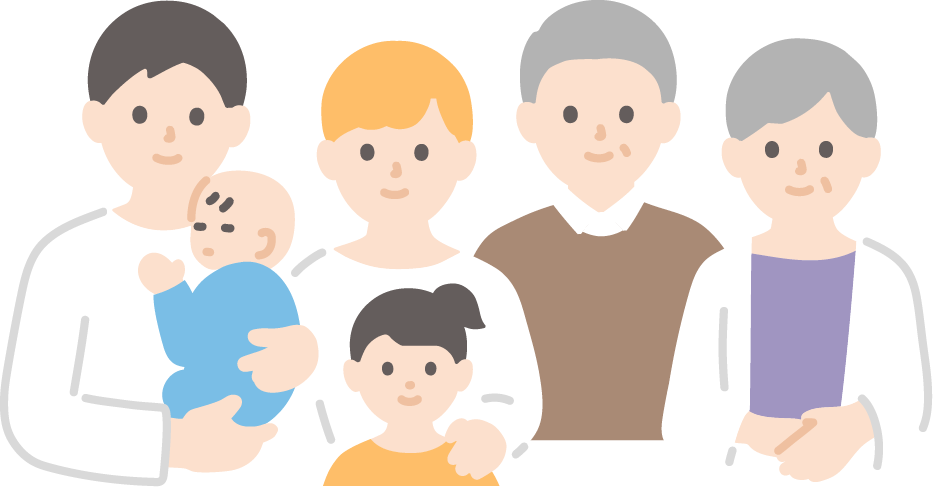
認知症の増加は止まらない
認知症の患者はこれからますます増え、経済に大きな影響を与えると考えられています。
2022年の時点で軽度を含めると高齢者の4人に1人が認知障害を持つと推計されています。
出所:厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」
さらに2040年には高齢者の46%が認知症になる可能性があるという推計もあります。
出所:ニッセイ基礎研究所「2023年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計」
また認知症患者が保有する金融資産は2030年度に215兆円に達し、家計金融資産全体に占める割合が1割になるという試算もあります。
出所:第一生命経済研究所「認知症患者の金融資産200兆円の未来」
認知症患者が増え、その人たちが所有する資産も増えていくという未来が見えているのです。
資産凍結のリスクが身近に
認知症になると、原則は本人だけでなく家族でも銀行口座から預金を引き出したり、不動産の売買などができなくなります。これを「資産凍結」といいます。
認知症になると正常な判断能力がない状態とされ、詐欺などから本人の財産を守るために資産の管理や処分ができなくなります。認知症の増加とともに、資産凍結のリスクがより身近なものになってきているのです。
認知症による資産凍結を避けるには
認知症による資産凍結を避ける対策として挙げられるのが「成年後見制度」と「家族信託」です。
「成年後見制度」は、判断能力が低下した人の財産を第三者が守る制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に変わって財産の管理や契約手続きを行います。
成年後見人に選任されるのは主に弁護士や司法書士などの法律の専門家です。
成年後見人は家庭裁判所の監督下で活動するので、財産を売却したり大きな支出をしたりする際は、裁判所の許可が必要となります。
手続きに時間がかかるなど使い勝手がよくないことから、あまり利用されていないとされています。
家族信託が注目されるわけ
そんななか注目されているのが「家族信託」です。
家族や親族に託すことができる
家族信託は文字どおり家族や親族に財産の管理や処分を託します。
例えば高齢の親が子供に財産の管理を任せることで、認知症になった場合でも財産を適切に管理・運用することができます。亡くなった際には相続を円滑に進めることができます。
具体的な使い方を決められる
財産の管理や運用方法を自由に設計することが可能で、「生活費として毎月一定額を配偶者に支払う」「不動産を売却して老人ホームの費用に充てる」など、具体的な使い方を決めることができます。
「遺言」として二次相続の指示もできる
また相続発生時の指示もできるので、遺言のような効果もあります。
さらに遺言では本人の相続人への渡し方しか指示できないのに対して、家族信託ではその先の二次相続の指示をすることも可能です。
認知症になる前に契約を
注意したい点は、財産の管理を委託したい人(委託者)が判断能力を持っているうちに、つまり認知症になる前に信託契約をする必要があるということです。
費用はいくらかかるのか
では、家族信託と成年後見制度の費用についてです。
家族信託の初期費用は信託する財産の額によりますが、70万円~100万円程度かかるとされています。
一般社団法人家族信託普及協会のHPでは、不動産を含む場合の初期費用の目安は信託財産額の1.5~2%としています。財産額が5,000万円であれば、75万円~100万円となります。
→「一般社団法人家族信託普及協会」
これは信託契約書を作成や不動産登記、専門家の報酬などです。
運用費用は家族との契約となるため、基本的にかかりません。
一方、成年後見制度の初期費用は家庭裁判所への後見開始の申立て費用の数万円程度です。
運用費用は成年後見人の報酬額で、裁判所が決定します。管理財産の額や選任される専門家によりますが、月額2万円~6万円です。
年間だと24万円~72万円となり、認知症になってから10年経過したとすると240万円~720万円になります。
長期的な視点で費用を考えると
家族信託は初期費用が成年後見制度よりも高額となりますが、柔軟な財産管理や相続対策が可能です。長期的な視点ではコストパフォーマンスがよい場合もあります。
家族信託の初期費用は一見、高額に思えますが、財産の規模や運用の自由度、相続対策への有効性などを考慮すると、一概に高額とは言えないのかもしれません。
一方、成年後見制度は初期費用は抑えられるものの、運用の自由度は低く、長期間利用すると運用費用が負担になるといえそうです。
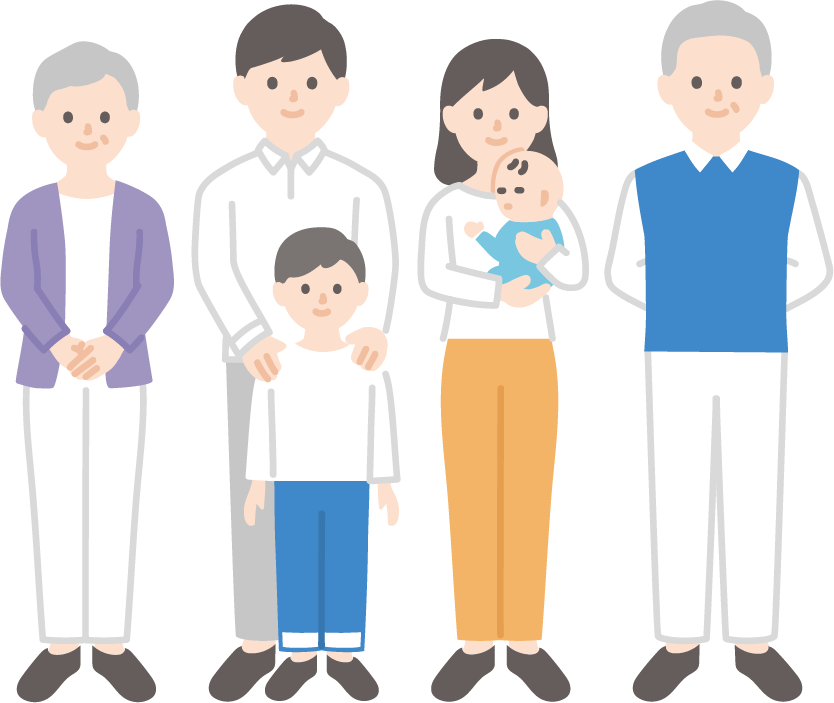
認知症への備えは早めに
成年後見制度は認知症になってからでも利用することができる制度です。一方、家族信託は認知症になる前に信託契約をする必要があります。
専門家に相談して、早めに準備することが大切です。
<用語>
家族信託 成年後見制度 成年後見人 後見監督人 被後見人 信託 委託者 受益者 受託者 二次相続 認知症 軽度認知障害(MCI) 資産凍結 信託法改正 商事信託 遺言信託業務 投資信託 契約信託 遺言信託 自己信託(信託宣言)


