「不動産小口化商品」の相続リスク

相続対策を考える中で、近年注目を集めているのが「不動産小口化商品」です。
本来は高額な不動産を、小口化して販売し、賃料収入や売却益を出資者に分配するという商品です。
1口数万円という商品もあり、不動産の特徴を持ちながら投資がしやすいということで、相続対策でも使い勝手がよいとして注目されているのです。
ただ仕組みがよくわからないことや、元本が保証される商品ではないため不安に思う人も多いようです。
今回は、この「不動産小口化商品」の仕組みや相続での活用方法などを、メリットやデメリット、そしてリスクも含めてわかりやすく解説します。

不動産小口化商品の仕組み
「不動産小口化商品」とは、1つの不動産を複数の投資家で「小口」に分けて所有し、そこから得られる賃料収入や売却益を分配する投資商品です。
相続対策で活用できる不動産に、少額から投資できるのが大きな特徴です。
仕組みは大きく2タイプ
1. 共有持分タイプ
不動産特定共同事業法(不特法)に基づきます。
複数の投資家が不動産に出資し、持分の比率に応じて賃料収入や売却益が分配されます。
2017年にインターネットで出資を募ることができるようになり、「不動産クラウドファンディング」と呼ばれることもあります。
出資や運営の形態によって、さらに3つに分類されます。
(1)任意組合型
出資した複数の投資家と事業者が共同で事業主体となります。
出資した不動産について、実物の不動産と同じく相続税評価額が計算されるので、
相続対策として活用できます。
長期運用向けです。
(2)匿名組合型
投資家は金銭を出資し、事業者が事業主体となって運営し投資家に利益を分配します。
1口数万円など少額での投資ができます。
不動産投資を始めてみたい方にお勧めです。数ヵ月での短期運用もできます。
(3)賃貸型
複数の投資家が不動産を購入し、事業者に貸し出します。事業者が実際の運営をします。
事業者が破産した際のリスクが大きいため、最近はこのタイプの商品は少ないようです。
2. 信託受益権型
不動産信託受益権は、金融商品取引法に基づきます。有価証券の一つとなります。
不動産信託された信託財産となっている不動産の受益権に少額投資します。
不動産を運用している信託銀行等が信託報酬などを差し引いた金額を投資者に分配します。
対象が高額な不動産でも、小口化されているので数100万円などから投資できます。
小口化して保有している信託受益権は、分割しやすいので相続対策として活用できます。
3つのメリット
メリット① 少額投資から一定の収益を得られる
不動産小口化商品は、通常数十万円から投資が可能です。中には1口数万円という商品もあります。
少額投資でも不動産投資に変わりはないので、賃料や売却益という不動産収益を得ることができます。
賃料は空室リスクはあるものの、一定の収益を見込むことができます。
例えば、1億円のオフィスビルを100口に分け、1口100万円の小口化商品の場合、
1口100万円を投資し、年間3%の賃料収入があると、年間3万円の分配金を得られることになります。
メリット② 手間がかからない
実物の不動産に投資する一般的な不動産投資では、物件の管理やメンテナンス、賃料の回収などさまざまな手間がかかります。
一方、小口化商品では不動産の管理や運用は事業会社が担当するので、投資家の手間がかかりません。
メリット③ プロの目線で投資できる
不動産小口化商品の対象となる不動産は、事業者がプロの目線で選んだ物件です。
事業会社は安定した賃料収入が得られ、将来的に売却益が見込める不動産を厳選します。
個人では投資が困難な大型マンションや商業施設などを、業界に精通したプロが選び出します。
4つのデメリット・リスク
デメリット・リスク① 元本が保証されない
ほかの多くの金融商品にも言えることではありますが、元本は保証されません。
不動産市況が悪化して、売却時に元本割れをするリスクがないとは言えません。
また、一定の賃料は期待できるものの、空室になってしまい賃料収入が想定を下回るというリスクもあります。
デメリット・リスク② 融資が利用できない
実物の不動産投資の場合は、対象不動産を担保に不動産ローンを利用することができます。
一方、不動産小口化商品は、融資を利用することができません。
すべて自己資金で投資することになります。
デメリット・リスク③ 利回りが低くなる
実物の不動産投資に比べて、利回りが低くなるとされています。
管理や運用の手間がかからない分、それらを事業会社が行います。その費用が差し引かれるため、利回りが低くなってしまうのです。
デメリット・リスク④ 思いどおりに売買できない
不動産小口化商品は注目されてきてはいるものの、十分な供給があるとは言えません。
そのため申し込みの倍率が高く、買いたくても買えないというケースがあります。
一方、売る場合にも思いどおりにいかないことがあります。
商品によっては途中解約ができないものもありますし、途中解約できる場合でも、
十分な流通市場があるわけではないので、買い手が見つからないと売れません。
相続での活用術とリスク
不動産小口化商品の相続対策での活用方法を、相続税の節税と遺産分割のポイントから解説します。
活用術① 相続税の負担を軽減する
相続財産は現金で保有していると、相続税の計算では額面通りに評価されます。
一方、不動産やその信託受益権は評価額が抑えられるため、相続税の評価額を減らすことが可能です。
不動産は土地と建物を分けて評価します。
土地は、相続税路線価で評価されることが多いのですが、路線価は売買価格の目安となる公示価格の80%程度とされています。
つまり時価の8割ほどで相続税では計算されます。
建物は固定資産税評価額で評価されます。固定資産税評価額は新築でも建築費の60%程度とされています。
このように、不動産はそもそも相続税の評価額が低くなるように設定されているのです。
これに加えて、不動産小口化商品は共有持分や信託受益権で所有されているため、小規模宅地等の特例が適用されることもあり、さらに評価額を下げられる可能性もあります。
リスク
評価額の軽減策が認められないケースがあるので注意が必要です。
例えば、小規模宅地等の特例では、適用の要件が細かく定められています。
小口化商品の不動産は「貸付事業用宅地」としてこの特例の対象になることがありますが、
所有してから3年以内に相続が発生した場合には、この特例が認められません。
相続税の軽減策があからさまな場合には税務署が認めないことも多いようです。
事前に税理士など専門家に相談することが大切です。
→参考:国税庁「小規模宅地等の特例」
活用術② 分割しやすくする
小口化した不動産は相続の際に、相続人に分けやすい資産だと言えます。
例えば、1億円の賃貸マンション1棟を所有していても、子供3人に分けるのは難しいですが、
1,000万円の小口化商品10口にしておけば、長男に4口、次男に3口、三男に3口などと分けやすくなります。
遺産分割協議になった場合でも、話し合いがスムーズに進むかもしれません。
リスク
不動産を小口化商品に組み替える際には、コストがかかることに注意が必要です。
手数料や登記料、取得税などさまざまな負担があるので、十分に考慮して進めましょう。
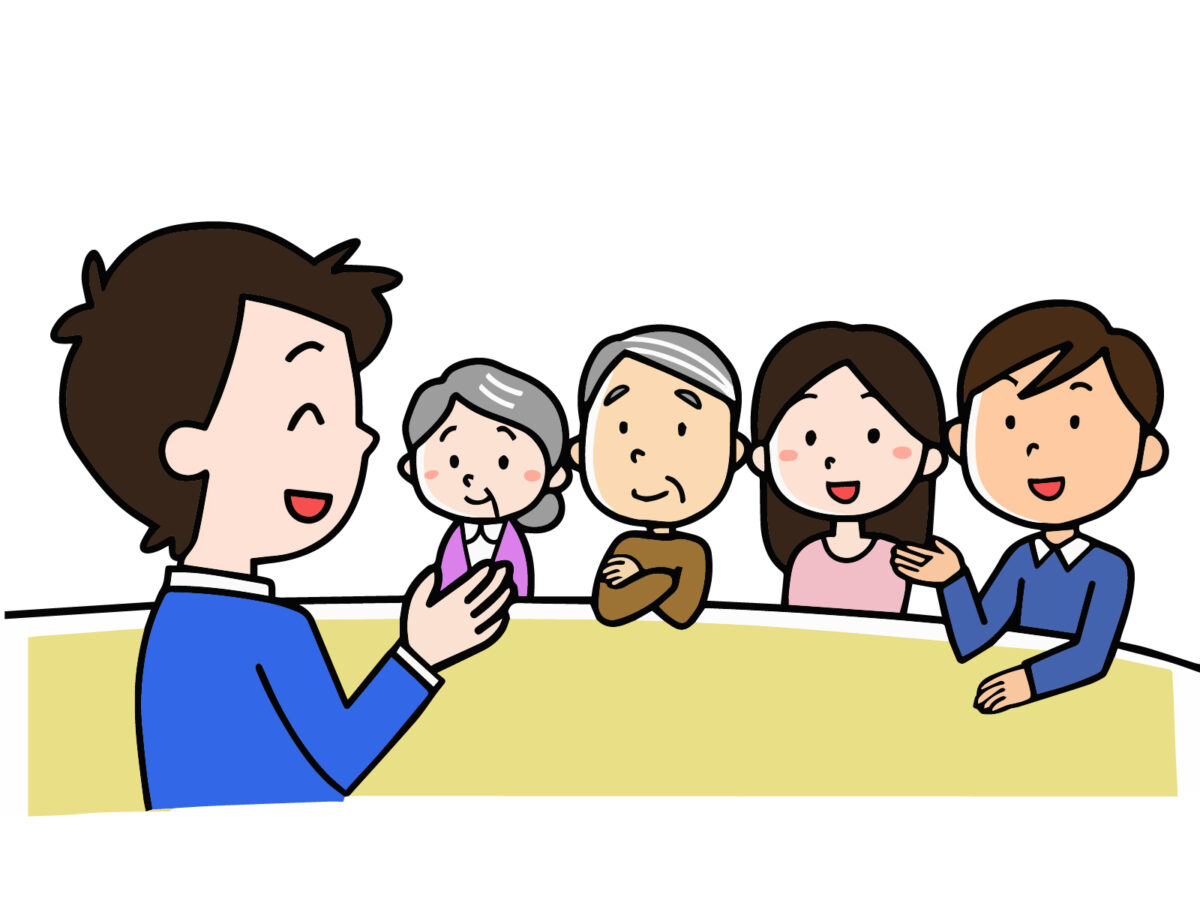
まとめ
不動産小口化商品は、相続対策の観点からも有効な手段です。
「相続税の負担軽減」「遺産分割のしやすさ」といった点で、メリットを発揮します。
ただし、商品の仕組みや内容、リスクを十分理解した上で、信頼できる税理士など専門家と連携しながら活用していくことが重要です。


